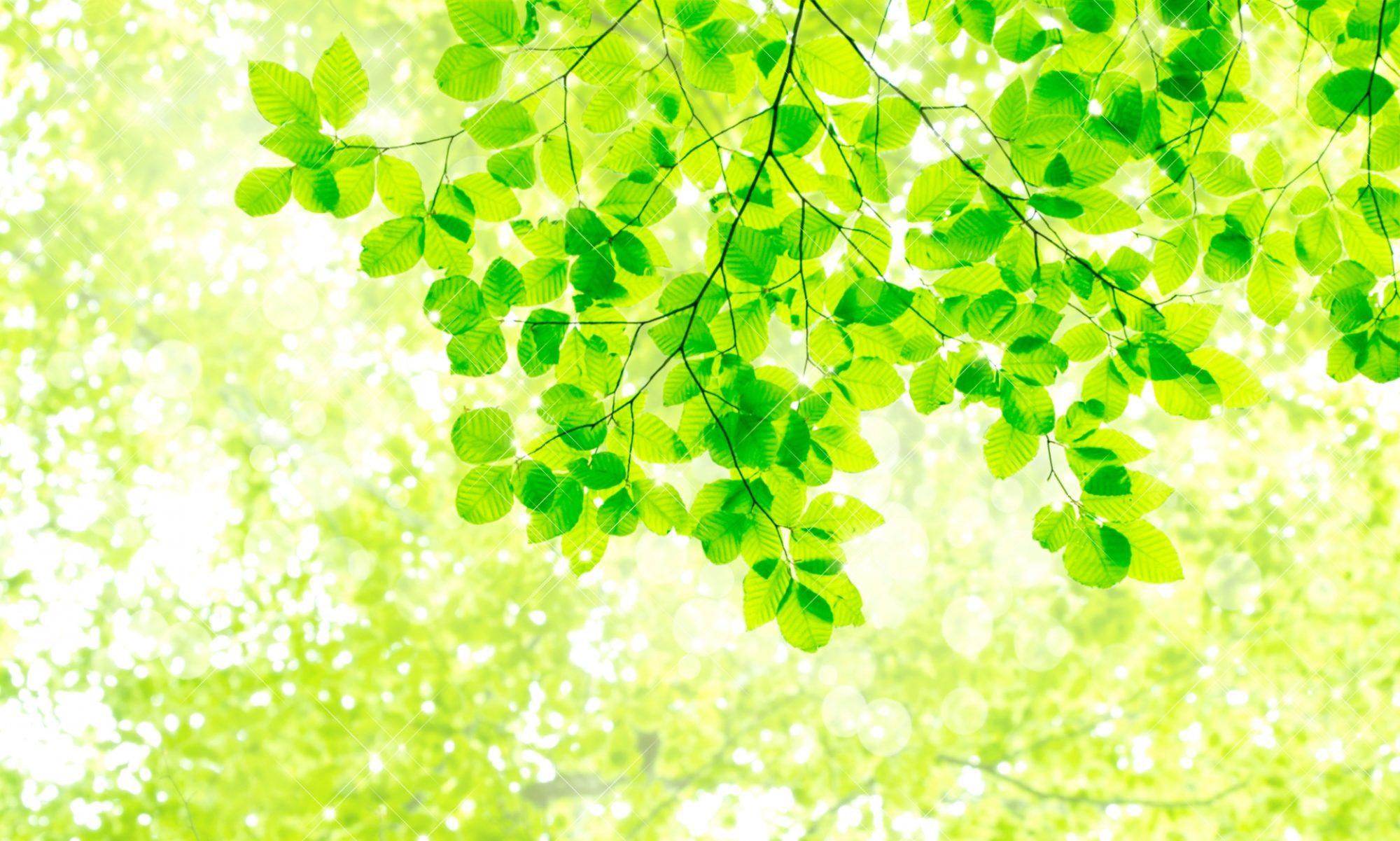柿は10月から11月頃が旬ですから、秋の味覚というより晩秋の味覚といったほうが良いかも知れませんね。
ところで、柿って体にいいの ?
ということで、今回は柿の効能について調べてみました。
「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざをご存知ですか?
これは、柿の実が赤くなるころは気候も良くなって病人が出にくいので医者が困ると言うことだそうです。
しかし、柿の健康効果を考えると、柿を食べると病気が予防されるから医者が困る、と言う解釈も成り立つのではないかと思えるほど、柿にはすぐれた効能があるのです。
チョット脱線ですが、ヨーロッパには「トマトが赤くなると、医者が青くなる」(A tomato a day keeps the doctor away. : トマトがあれば医者いらず)ということわざがあります。
トマトについては別の記事でお伝えしますね。
柿の栄養素ってなに ?
柿の効能を知るために、まず柿の栄養素を確認しておきましょう。
柿の主な栄養素は次の通りです。
・ビタミンC
・β-カロテン
・タンニン
・ペクチン
それでは、柿にこれらの栄養素が含まれていることを踏まえたうえで柿の効能を見ていきましょう。
柿の効能 生活習慣病を予防 !
タンニンとβ-カロテンには、強い抗酸化作用があり、コレステロールの酸化を抑えて動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果が期待できます。
柿の効能 口臭を抑える !
タンニンには、抗菌、消臭作用があることが知られています。
口臭の原因のひとつに、食べかすなどが細菌で分解されてできる揮発性硫黄化合物があげられます。
タンニンは、口臭の原因となるこの揮発性硫黄化合物と結合して無臭の物質に変えてしまいます。
また、原因菌の増殖を抑える抗菌作用もありますから、口臭を消す効果が期待できるのです。

柿の効能 二日酔いに !
タンニンには、二日酔いの原因物質であるアセトアルデヒドと結合して体外に排出させる作用があって、昔から二日酔いに効くと言われています。

柿の効能 免疫力を高める !
ビタミンCは免疫物質を作る上で欠かせない栄養素で、粘膜の働きを正常に保つ働きもあります。
また、タンニンとβ-カロテンにも免疫力を高める作用があることが知られています。
柿の効能 美肌効果 !
タンニンには、肌を引き締める効果がありますので、開いた毛穴を引き締めて肌を整えてくれます。
また、ビタミンCには美白効果がありますから、柿を食べると美肌になると言われています。

柿の効能 整腸作用 !
ペクチンは水溶性の食物繊維で、便通を整える作用があります。
また、タンニンの収れん作用は腸にも働いて、腸のぜん動運動を促しますので、ペクチンとの相乗効果が期待できます。
効能の多くに、タンニンが関わっていることにお気づきと思います。 じつは、タンニンは柿の渋味の元でもあるのです。 では、上記の効能は渋柿だけのもので、甘柿にはないのでしょうか ? ご心配なく、甘柿にもちゃんとタンニンが含まれていますよ。
渋柿のタンニンは水溶性なので、口の中で唾液に溶けて渋味を感じますが、甘柿のタンニンは熟す過程でタンニンが不溶性に変わってゆくので、口の中で渋味を感じないんです。

タンニンには鉄と結合して、その吸収を妨げる性質があります。 ですから、貧血気味の方は柿をたくさん摂らないよう、注意が必要です。 また、整腸作用があると言っても、食べ過ぎるとかえって便秘や下痢をおこすことになりますので、何でもそうですが、ほどほどがよろしいようですよ。
おわりに
柿は美味しいだけでなく、こんなに健康に良い効能があったのですね。
これから、柿を食べるのが一層楽しみになります。
ところで、「桃栗三年柿八年」と言いますが、柿は実がなるまでに本当に8年もかかるのでしょうか?
はい。本当なんです。7~8年かかると言われています。
でも、接ぎ木をすることで、結実は早まり、3~4年で収穫することができるそうです。
これを発見した人はすごいですね。
おかげで私たちは、毎年美味しい秋の味覚である柿を、潤沢に食することができるようになりました。
感謝ですね !
最後までお読みくださってありがとうございます。
この記事がお読みくださったあなたの役に立てばうれしいです。