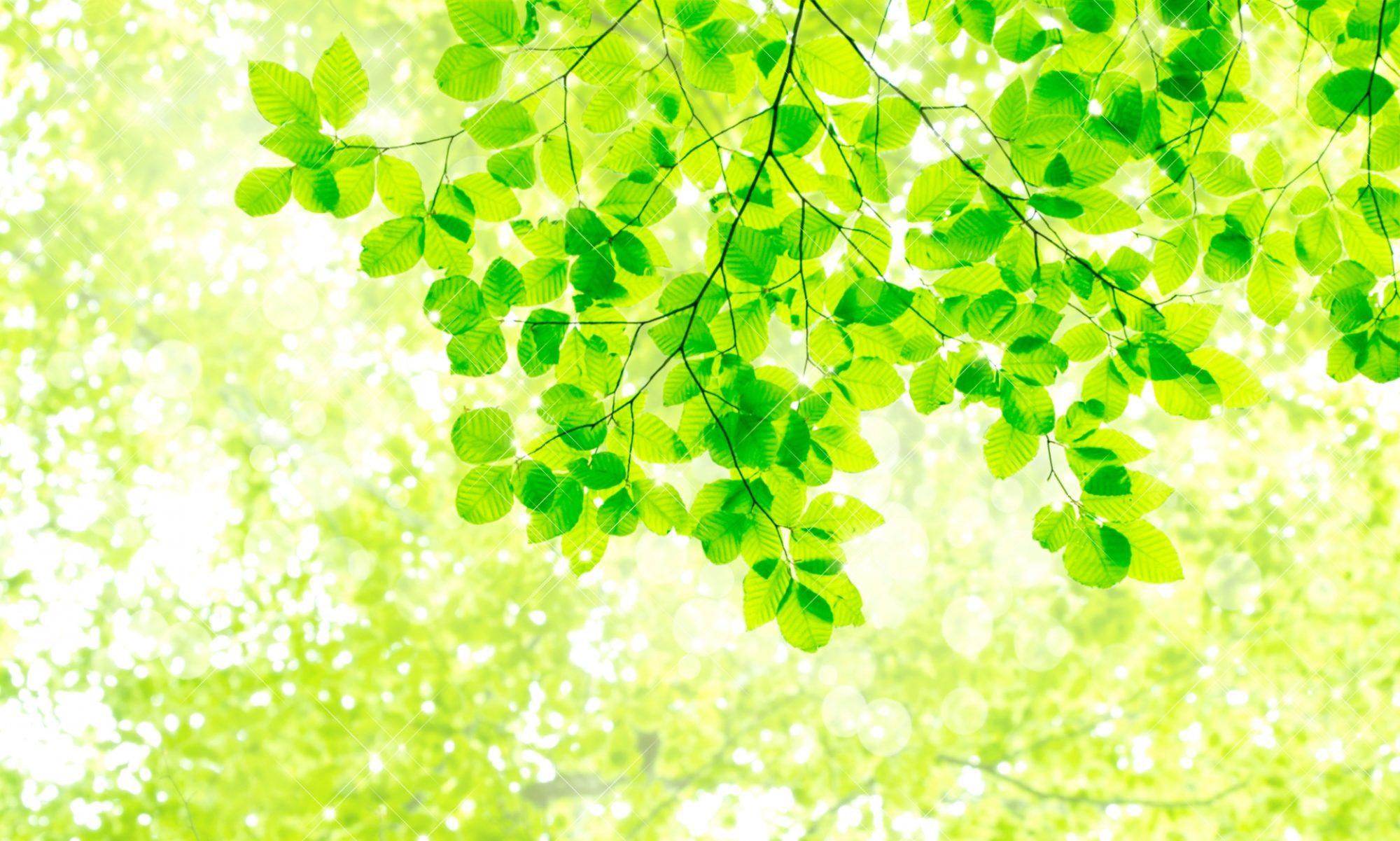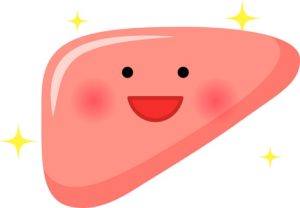夏野菜と言えば、キュウリ、ナス、トマト、ピーマン、オクラ、トウモロコシ、ニラ、カボチャ、ズッキーニなど、いろいろありますが、今回は、その代表格ともいえるトマトを取り上げてみました。
数ある野菜のなかで、そのままジュースにして飲めるのは、何といってもトマトですよね。
爽やかな酸味とほのかな甘み、そして旨みのあるトマト。
じつは、トマトには旨み成分である「グルタミン酸」が豊富に含まれているのです。
イタリアなどの地中海に面した国々では、トマトソースを調味料として、日本の味噌・醤油のように使っています。
トマトと味噌・醤油は、どちらも旨み成分の「グルタミン酸」がたっぷりと含まれている点で共通していたのですね。
ですから、トマトはほかの食材と相性がよく、一緒に調理すると肉や魚の旨みを引き出してくれるのです。
トマトの健康効果
トマトは美味しいだけでしょうか?
じつは、トマトには優れた健康効果があるのです。
ひとつずつ見てゆきましょう。
疲労回復・夏バテ防止
トマトの酸味は、クエン酸によるものです。
クエン酸には食欲を増進させる効果や、疲労物質である乳酸を分解する働きがあります。
また、トマトには糖質をエネルギーに変えるビタミンB1も豊富に含まれているのです。
ですから、トマトは疲労回復や夏バテ防止にもってこいの野菜なのです。
トマトが夏野菜の代表格というのが頷けますね。
生活習慣病と老化防止
トマトの真っ赤な色は、リコピンという色素によるものですが、リコピンには強力な抗酸化作用があるのです。
そのため、余分な活性酸素を抑えて生活習慣病の予防と老化防止に効果があると言われています。
さらにβカロチンも含まれていて、免疫力を高め、皮膚や粘膜を健康に保つ効果も得られるのです。
さらに、近年、トマトの種子に含まれるトマトシドAというサポニンの一種に、コレステロールの上昇を抑制する作用のあることが発見されたと言いますから、トマトの健康効果はますます見逃せませんね。
塩分摂りすぎの抑制
トマトの効能はまだあります。
トマトに含まれているカリウムは、余分なナトリウムを体外に排出させる働きがあり、塩分の摂りすぎを抑制して、高血圧の予防に効果があるのです。
トマトの美容効果
トマトは健康だけでなく、美容にも効果があります。
先にのべたリコピンとβカロチンの抗酸化力は肌の酸化を抑えるので、シミやシワの発生を抑えてくれるます。
さらに、ビタミンCも多く含まれています。
ビタミンCは、コラーゲンの生成に欠かせない成分ですから、美肌のためにもトマトは強い味方となるのです。
おまけ
トマトは、南米ペルーのアンデス高地が原産地のナス科の植物。
トマトがナス科 ? ご存知でしたか ?
ちなみにジャガイモもナス科です。
そう言われれば、色は違いますが、どれも花の形は良く似ていますね。
(左から、トマトの花、ジャガイモの花、ナスの花)



おわりに
如何でしたか ?
疲労回復・夏バテ防止、そして生活習慣病と老化防止効果 !
その上美容効果もある !
身近な食材であるトマトには、うれしい効果がいっぱいあったんですね。
やっぱり夏野菜の代表ですね。
トマトを大いに活用して美容と健康に役立てましょう !